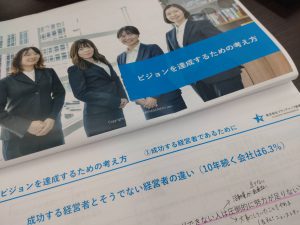自社の経営方針発表会より
こんにちは、伊藤です。
2月1日は当社の経営方針発表会でした。
当社は代表の長尾が個人事務所として創業し14年目、法人化して第7期目となります。
経営方針発表会では、昨年度の振り返りと、中期計画、今期計画の発表がありました。
雇用を生み、利益を出し、社員が働き続けるために
「日本の平均年収の3倍の年収を常に生み出す会社にする」
「計画5年目(2028年12月期)には従業員30名、売上10億円の規模を目指す」というミッションも発表されました。
代表の長尾からは当社の経営ビジョン、経営戦略、
ビジョン達成のためにはどのような考え方を持つべきかなどの共有がありました。
日常で聞く内容と重なる部分もありましたが、
経営方針発表会という形で改めて聞くことで、身の引き締まる思いとなりました。
今後の会社の方向性を知ることにより、
「今後のフラッグシップ経営で自分はどうありたいのか。」「どうあるべきなのか。」「今の自分の状態は?」など、
未来の会社の姿から未来の自分に落とし込み、現状とのギャップ、目的達成のための課題、今後の何をどう取り組むべきかなどを改めて考えることもできました。
本年度も当社と出会った事業者様に喜んでいただけるよう尽力して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
伊藤 侑加