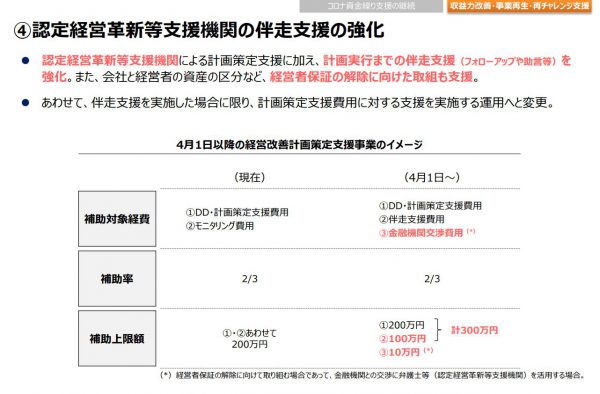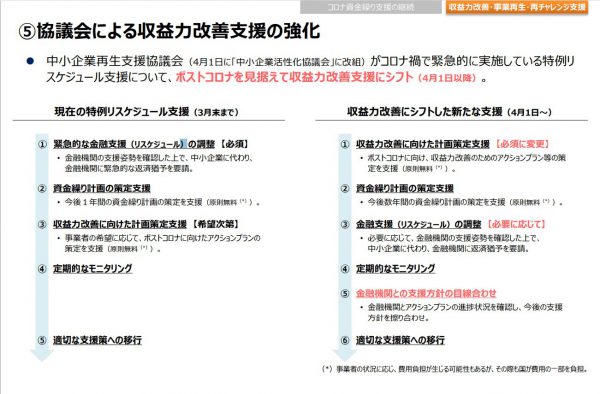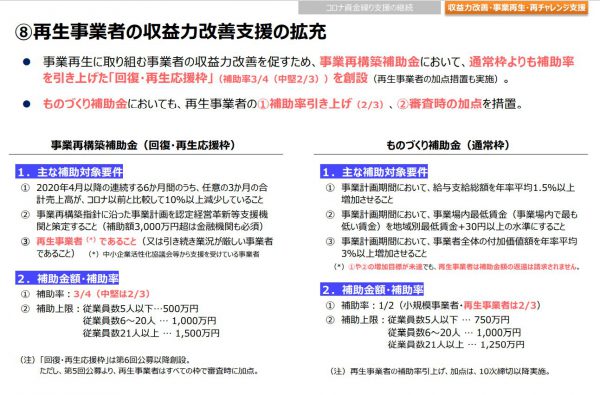会社の内部に成果はない
こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
事業を拡大しようと思うと既存の市場でシェアを増やすか新商品を販売するか新市場を開拓するか、または全く新分野へ事業領域を広げなければなりません。
しかし、事業が拡大すると会社内部へ視点が移り、社員のモチベーションアップやチームワークを良くすること、業務を効率的に回すことなど社内の「人と仕事」のマネジメントが増えていきます。
そして、多くの経営者が組織の管理や運営に時間と労力を注ぐのですが、会社の内部には「コスト」しかありません。売上は常に会社の外側にあり、市場には顧客と競合しかいません。
もちろん、生産性向上や品質向上、コスト削減、クレーム低減、職場環境改善など「お客様の要望を満たすための内部体制構築」に一定の時間を使う必要はあるのですが、やはりメインは外に目を向けなければなりません。
特に新型コロナが感染拡大し、事業環境が大きく変わった約2年間に視点を外に向け、新しいお客様をつくりだす活動をどれだけ行ってきたかの差が、会社の業績に出始めているようにも感じます。
最近、「内部の管理に時間や思考と使っているな」、「あまりお取引先やご紹介先様などを訪問していないな」と少しでも感じられた方は、一度、視点を会社外へ移してみてください。
中小企業診断士 木戸貴也