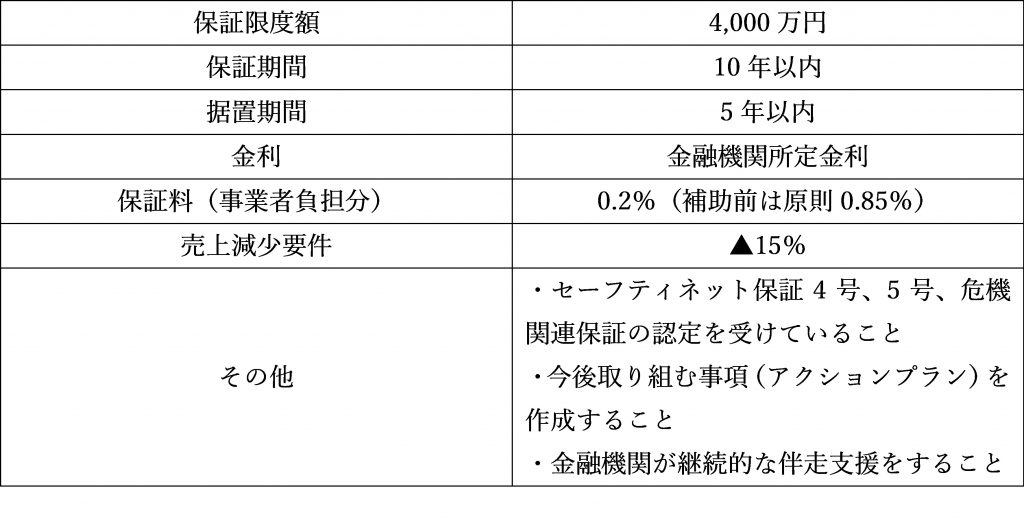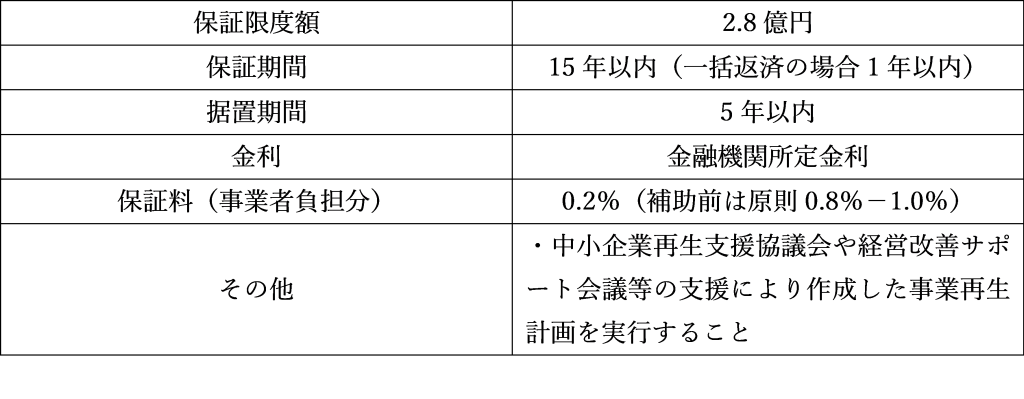事業再構築補助金とは
企業の思い切った事業再構築を支援
(中小企業等事業再構築促進事業)
対象
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します!
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月 の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に 取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
中小企業
・通常枠 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
・卒業枠 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
*400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
中堅企業
・通常枠
補助額 100万円~8,000万円
補助率 1/2(4,000万円超は1/3)
・グローバルV字回復枠
補助額 8,000万円超~1億円 補助率1/2
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
令和2年度3次補正予算案において実施予定 「経済産業省HPより抜粋」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
事業再構築補助金について、概要をまとめました。
本制度に、ご興味をお持ちの方は是非当社までご連絡ください。