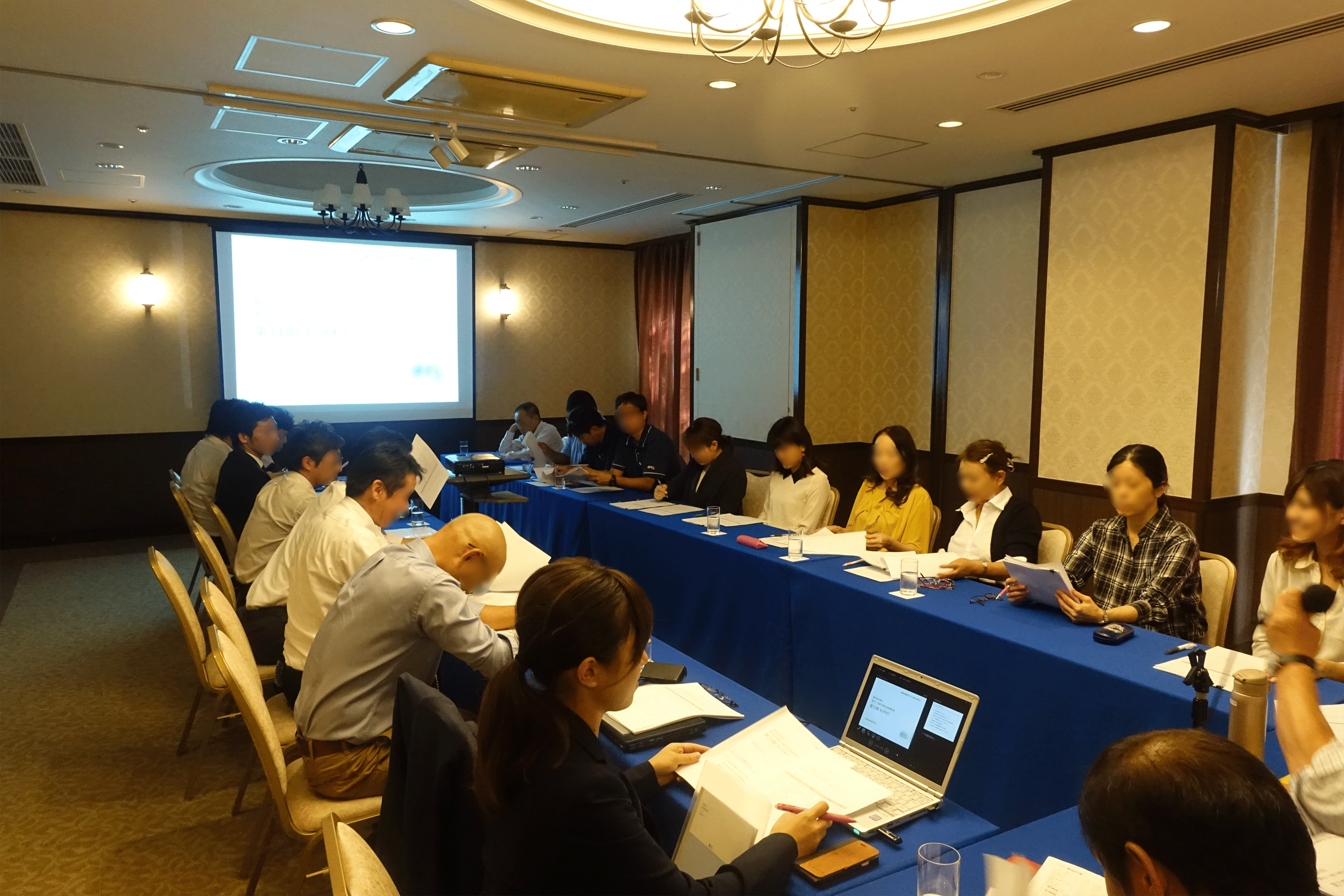皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表の長尾です。
今日は経営における「自由」について考えたいと思います。
「社長はいいですね、誰にも縛られず、自分の好きなようにできて」
経営者仲間や、時には社員からも、冗談混じりにそんな言葉をかけられることがあります。
しかし、このブログを読んでいる経営者の方ならそれが大きな誤解であるとお分かりいただけると思います。
組織において「最も不自由な存在」はトップである経営者自身です。
世間のイメージとは裏腹に、経営者は「したいこと」を自由に選べる立場ではありません(中には本当に自由にしていて会社が無茶苦茶になっている事例はありますが・・・)
むしろ、経営者が「自分のしたいこと」を優先し始めた瞬間、会社がおかしくなり始めます。
経営者は常に「経営方針」や「企業の社会的責任」、そして「市場の要求」という強力な力に拘束されています。
そこにあるのは「やりたいこと」ではなく、常に「すべきこと」です。
経営者が向き合っているのは解決しなければならない問題、決断を迫られる不都合な事、そして「したくないが、組織のためにせざるを得ないこと」の連続です。
不採算部門の整理、苦渋の決断を伴う人事、市場変化への無理な適応。
これらは決して「楽しいこと」ではありません。
しかし、経営方針に従う以上、私情を挟む余地はそんなにありません。
さて、この「経営者の不自由さ」は幹部にも当てはめるべきではないかというのが私の持論です。
多くの組織において、問題は「幹部が自由すぎる」ことから生じます。
「自分の部署の利益だけを考えたい」「部下に嫌われたくないから厳しいことは言いたくない」「自分の得意な仕事だけをしていたい」。
これらはすべて、幹部個人の「したいこと(私心)」です。
しかし、幹部とは経営者の分身であり、経営方針を具現化する存在です。
彼らが自分の感情や好みで動いているうちは、組織は一つの方向を向くことはできません。
幹部が「経営方針という拘束」を自ら受け入れ、「自分はこの方針の遂行者である」という自覚を持ったとき、組織の実行力は劇的に高まります。
例えば、幹部が経営者と同じ視点に立ち、「したくないが、せざるを得ないこと」を淡々と、かつ情熱を持って実行できるようになると、組織には独特の「規律の美しさ」が生まれます。
1. 意思決定のスピードアップ: 「好き嫌い」ではなく「方針に沿っているか」が基準になるため、会議から無駄な忖度が消えます。
2. 現場への一貫性: トップから末端まで「なぜこれをやるのか」という理由が私心なき方針に基づいているため、社員の納得感が深まります。
3. レジリエンス(復元力): 困難に直面した際も、感情に流されず「なすべき最善」に集中できるため、立ち直りが早くなります。
幹部が「私も社長と同じく、この方針のために不自由になる覚悟があります」と言える組織。そんな組織が、強いでしょう。
私たちは、自由を求めて経営をしているのではなく、成し遂げるべき使命のために、不自由を選んでいます。
自由、個性、効率などという言葉が軽く使われている現代のビジネスシーンですが、何かを成し遂げるというのは不都合な自由を受け入れる人数で決まってくるのだと思います。
こんにちは、営業事務の造田です。
日々の仕事や学生時代の経験の中で、「とにかくすぐ動く人」と「じっくり考えてから動く人」の2つのタイプが見られると感じています。
どちらにも良さはありますが、結果的に成果につながるのは、どちらか一方に偏るのではなく、両方の良いところを取り入れたバランスです。
今回は、スピードと質を両立させるための考え方をご紹介します。
まず、「とにかくすぐ動く人」の特徴はスピードが早くチャンスを逃しにくいことや、周囲を巻き込みやすいという強みがある一方で、目的があいまいなまま進めてしまうことや手戻りが増えて結果的に時間がかかることがあるという注意点があります。
次に「考えてから動く人」の特徴は全体像を把握し、ミスを減らせることや無駄な作業を減らせられる一方で、着手が遅れてしまったり考えすぎて動けなくなったりするというデメリットが挙げられます。
両方の良さを取り入れることができる人は、「小さく考えてすぐ動く」ことを意識しており、これを実現するためには次の3つのポイントが大切です。
① 目的だけを決めて、まず動く
完璧な計画を作ろうとせず、「何を達成したいか」を明確にして行動する。
② 小さく試して考えながら修正する
最初から正解を出そうとせず、実際に手を動かしながら軌道修正することで、スピードと質を両立する。
③ 途中で立ち止まる時間を入れる
ずっと走り続けるのではなく、方向性がずれていないかを確認することで、無駄な手戻りを防ぐ。
このサイクルを意識して回すことでスピードと質の両方を手に入れることが出来ます。
日々の業務の中に小さな工夫を取り入れ、より良い成果に繋げていきたいと思います。
造田朋夏
経理・総務の松野です。
最近の業務で、社内の「ルールブック」を作成しました。
きっかけは、日々の業務の中で「これってどうするんだっけ?」と迷う時間を減らし、チーム全員で共通認識を持ちたいと考えたことです。の運用をもとに、誰も更新ができるGoogleのスプレットシートで作成しました。
このルールブックの特徴は、会社の中で当たり前になっていることも明文化している点です。
現時点では、
社用携帯の取り扱い
ブログの更新手順
未入金が発生した際の連絡フロー
来客時の対応マナー など
このルールブックは、誰でも内容を追加・更新できるようになっています。
早速、コンサルタント職のメンバーが項目を付け加えてくれました。
作成してみて気づいたのは、「自分にとっての『当たり前』は、決して他の誰にとっても同じではない」ということです。
整理することで、「そんなルールがあったのか」という新しい発見や、「〇〇さんがずっと対応してくれていたんだ」という感謝が生まれるきっかけになると感じています。
また、ルールとして明文化されていることは、育成の場面でも大きな助けになります。後輩へ指導する際も、個人の価値観による注意ではなく「会社のルール」として伝えることで、教える側・教わる側双方の心理的なハードルが下がると考えています。
もちろん、すべてがルール通りにいかない例外もあるはずです。
「ルールブックを読んでおいて」で終わらせるのではなく、日々の何気ない声がけや、お互いのフォローがあってこそのルールブックであると感じています。
前回策定した「行動指針」と同じように、これも作って終わりではありません。
状況に合わせてみんなで内容を書き換えたり、「もっとこうしよう」と話し合ったりしながら、チーム全員で共通認識を持つためのルールブックにしていきます。
経理・総務 松野あやか