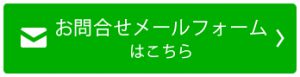早期経営改善計画 とは
平成29年5月10日、中小企業庁よる「早期経営改善計画」の策定支援事業がスタートしました。
経営改善をしたいとお考えの中小企業・小規模事業者の皆様にはぜひ活用して頂きたい制度ですので、詳しくご紹介させて頂きます。
※追記:早期経営改善計画についての特別紹介ページを公開しました。
制度活用のメリットや申請の流れについて、分かりやすく説明しています。
>>> 早期経営改善計画とは
<こんな方にオススメ>
・最近、資金繰りが不安定になっている
・自社の状況を客観的に把握したい
・専門家から経営に関するアドバイスが欲しい
・損益計画や資金繰り計画を作りたい
・経営改善の進捗についてフォローアップしてほしい
1.制度の概要
中小企業庁のホームページには、以下のように記載されています。
本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。
つまり、資金ショート寸前で今すぐ金融支援が必要!といった緊急事態に陥ってしまう前に、
外部専門家に依頼して「早期経営改善計画」を策定し、金融機関(メイン行または準メイン行)に提出しましょう。それをキッカケに自社の経営改善に取り組んでいきましょう。計画策定にかかった費用の3分の2(上限20万円)は国が負担します、という制度です。
ちなみに、条件変更などの金融支援をうけるための計画策定は別の「経営改善計画策定支援事業」という制度が活用できます。名称が似ているのでご注意ください。
「経営改善計画策定支援事業」については以下でご紹介しています。
>>> 経営改善計画策定支援事業 とは
2.事業者にとってのメリットは?
以下のようなメリットが考えられます。
・自社の経営を見直すことで、今まで気づいていなかった経営課題を発見できる
・少ない費用で外部専門家から経営のアドバイスを受けられる
・資金繰りを正確に把握できるようになる
・金融機関との関係が良好になる
・資金ショートなどのリスクを事前に防ぐことができる
3.対象となる事業者は?
中小企業・小規模事業者であるとともに、以下の3つを満たしていることが必要です。
(1)条件変更などの金融支援を必要としていないこと
(2)これまでに経営改善計画を策定したことがないこと
(3)過去にこの制度を活用したことがないこと
※社会福祉法人、LLP(有限責任事業組合)や学校法人は除くなど、支援の対象とならない業種もありますので、ご注意ください。
4.制度活用の流れ
(1)外部専門家(認定支援機関)や金融機関、経営改善支援センターに相談する
(2)利用申請の手続き
(3)早期経営改善計画を策定し、金融機関へ計画を提出する
(4)費用申請の手続き
(5)費用の3分の1を外部専門家に支払う
(6)1年後に外部専門家によるモニタリングを受ける
中小企業庁のホームページにこの制度についての詳細が記載されていますので、ご確認ください。
>>> 資金繰り管理や採算管理等の早期経営改善計画の経営改善を支援します (新窓)
また、当社でも外部専門家として「早期経営改善計画」策定をご支援させて頂きます。
この制度について詳しく聞きたい、検討してみたいという方はぜひ一度ご連絡ください。
コンサルタント
住吉いずみ